民法改正後の「身元保証証」に関する変更点
会社の経営者や、労務担当者にとって、2020年4月からの「民法改正」の内容は、非常に重要なものとなっています。なぜなら、「身元保証書」に対する扱いが変わったからです。
採用が決まった者に対し、身元保証書の提出を求める会社は多いですが、記載された賠償金に対しては「会社に損害を与えた場合に、身元保証人が連帯責任を負う」というような曖昧な書き方が多く見られます。
しかし、今後は損害賠償金額の「上限金額」が記載されていないと、身元保証書自体が無効と見なされることになりました。
本記事では、身元保証書に関して「会社がやるべきこと」や「具体的な損害賠償金額の上限」などについて、詳しく解説します。
就業規則に身元保証書の規程は必要か?
身元保証書は、採用が決まった人に対し提出を求める書類で、主に下記2つを目的とします。
- 【目的①】
経歴・素行などに問題が無いことについての保証 - 【目的②】
万が一会社に損害を与えた場合に、保証人と連帯して損害賠償責任を負う
また身元保証書に関して、就業規則にも規程を設けるべきかと、悩まれる担当者もいるでしょう。規程を設けなくても法律上問題はありませんが、載せておく方が望ましいと言えます。
その理由は下記の通りです。
【理由①】身元保証書の提出は、義務ではない
就業規則に「身元保証書の提出」について記載がなければ、提出を拒否されても会社は何もできません。
このようなことを避ける為に、就業規則に「身元保証書の提出」を義務とし、提出を拒否する者には、採用取り消しが可能な旨も記載すると良いと言えます。
【理由②】社員がメンタル疾患を抱えた場合に、身元保証人に相談するケースがある
社員がメンタル疾患を抱えた場合に、勤怠不良や素行不良を起こすなど、リスクを抱えることがあります。このような時に、問題解決に協力してもらう為に「身元保証人」がいると安心です。
基本的に身元保証人は、社員のことをよく知っていることが多いので、解決の糸口が見つかることもあるでしょう。その為にも、就業規則に「身元保証書の提出」を義務とする旨を、記載すると良いと言えます。
民法改正で身元保証人の損害賠償金額の上限が義務化に!その背景は?
2020年4月より「身元保証人の損害賠償金額の上限」が記載されていない身元保証書は無効となり、「会社」と「身元保証人」の双方で、上限額の合意が必要になりました。但し、2020年4月より前に交わされたものに対しては、損害賠償金額の上限の記載が無くても、効力はそのまま続いています。
今回の民法改正で、損害賠償金額の上限記載が義務化になった背景には、身元保証人の「保護強化」があります。身元保証人としても、万が一の場合に、どれだけの金額を負担することになるかが明確でないと、不安になるものです。その為に、きちんと金額の上限を記載することになりました。
会社が具体的にやるべきこととは?
身元保証書に、身元保証人の損害賠償金額の上限を記載する必要があると分かりました。
それでは、会社として具体的にやるべきことについて、解説いたします。下記に内容をまとめました。
損害賠償金額の上限額を決める
損害賠償金額をいくらにするかという法律は無いので、上限金額は会社判断で自由に決めることができます。しかし、低い金額設定だと意味がありませんし、あまりに高額だと身元保証人が見つからないですとか、場合によっては入社辞退になる可能性もあります。また、実際に損害を被り、損害賠償請求をする場合の金額は、最終的には裁判所の判断になります。
このことから、相場を参考にした上限金額を定め、そのうえで身元保証書には「最終的には裁判所の判断による」と記載すると良いでしょう。上限の相場としては、100万~1,000万とする場合が多く、給与額を考慮した表記(例えば、給与の24ヶ月分)をする会社も多いです。
上限額を定めた書面で、運用を開始する
2020年4月以降に入社した社員には、①で定めた金額を記載した「身元保証書」を渡し、それをもとに運用を開始します。
2020年4月より前に入社した社員の場合は、具体的な金額が記載されていない書面のままでも効力は続きますが、上限額が記載された書面で再度取り交わすこともアリでしょう。
具体的な金額が記載された書面の方が、現実味が出るので、抑止力が出てくるからです。
まとめ
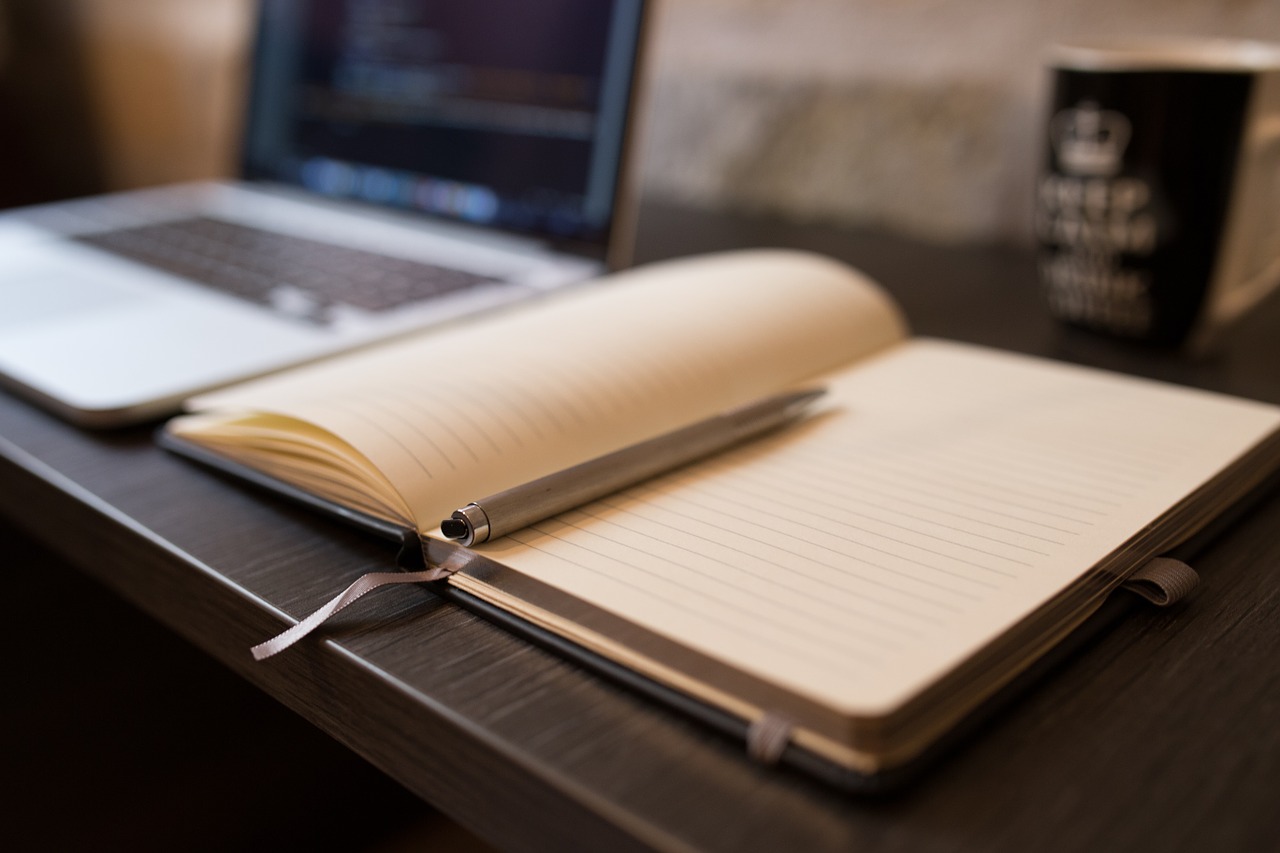
今回は、身元保証書に関して「会社がやるべきこと」や「具体的な損害賠償金額の上限」などについて、解説いたしました。私は長年労務担当として働いていますが、メンタル疾患を抱える社員が増え、問題を起こすケースが増えていることも実感しています。そのような時に、身元保証書をきちんと取り交わしていたので、身元保証人に相談して解決できた事例も多くありました。
損害賠償については、実際に起こさなくて済むことが望ましいです。しかし、上限金額が記載されていることにより、問題の抑止力に繋がることが期待できるので、身元保証書を交わすことは、会社と社員の双方にとって安心な環境を作れると言えるのではないでしょうか。





