物価上昇を受け、インフレ手当の導入を検討する企業が増えてきています。本記事では帝国データバンクと東京商工リサーチのインフレ手当に関する企業実態アンケート結果をもとに、インフレ手当支給の現状を紹介します。また、インフレ手当を支給する場合の注意点についても解説しますので、貴社でのインフレ手当支給検討の参考にしてください。
インフレ手当を支給する会社が増えている
まずはインフレ手当を支給または検討している企業の実態を確認してみましょう。
支給への取り組み状況
帝国データバンクの「インフレ手当に関する企業の実態アンケート」によると、2022年11月の調査時点で調査対象企業中6.6%の企業が物価高騰をきっかけとした特別手当(インフレ手当)を支給しています。まだ支給はしていないが、支給予定という企業(5.7%)や支給を検討中の企業(14.1%)を加えると26.4%となります。つまり、4社に1社がインフレ手当への取り組みをしていることになります。
一方、63.7%の企業は「支給する予定はない」との回答です。ただし、これらのなかには一時的な手当ではなく、「ベースアップ」でインフレ対応に取り組むという企業もあります。このことから、従業員への生活支援に取り組む企業は4社に1社よりも多いと考えられます。
支給方法
インフレ手当の支給方法には一時金や月々支給する方法などがありますが、前出調査では一時金で支給する企業が66.6%、月額手当とする企業は36.2%となっており、一時金として支給する企業が多いことがわかります。なお、一時金として支給する場合でも賞与に追加、月額手当の場合は一定期間の期限を決めて支給する企業が多い傾向です。
なお、一時的な手当ではなく、4月の定例賃金改定時に「例年よりも賃上げ幅を高めにする」という企業もあります。
平均支給額
インフレ手当の平均支給額を見ると、一時金の場合が5万3,700円、月額支給の場合は6,500円という結果でした。
一方、東京商工リサーチが上場企業に対して実施した「物価高に伴う上場企業『賃上げ・手当支給』調査」によると、支給金額が判明した上場25社の平均額は6万7,120円とより高めです。ちなみに、最高額はサイボウズ株式会社の15万円でした。
【参照】東京商工リサーチ「物価高に伴う上場企業『賃上げ・手当支給』調査(2023/2/10)」
インフレ手当を導入する際の注意点
物価上昇は現在(2023年5月執筆時点)も継続しています。これまでインフレ手当について考えていなかったけれども、導入を検討するようになったという企業もあるかもしれません。インフレ手当の支給に関しては気をつけるべき点がいくつかありますので、以下のような注意点を意識して検討するようにしましょう。
支給条件を明確にする
インフレ手当は、本来、物価上昇に対する従業員への生活支援という意味を持つ手当です。「支給の対象となる従業員の範囲」や「支給額」はもちろんのこと、支給方法や支給期間などの条件を明確にしておくことが必要です。
とくに支給額に差を設ける場合には合理性があるかどうかにも注意が必要です。世帯構成や生活様式によってインフレによる生活への影響に違いはあっても、物価上昇率自体が従業員間で異なるものではないからです。後々のトラブルを招かないよう、あらかじめ支給基準を明確にしておきましょう。
事例紹介
参考として、実際にインフレ手当を支給している企業の例を紹介します。
【事例①】株式会社コロプラ
株式会社コロプラでは、「インフレサポート特別手当」として契約社員を含む社員を対象に、2023年1月~12月まで(12ヵ月間)一律月額1万円を支給しています。
【事例②】株式会社すかいらーくホールディングス
株式会社すかいらーくホールディングスでは、正社員、嘱託社員、社会保険加入のパート・アルバイトを対象に「特別一時金」として2023年3月支給給与と合わせてインフレ手当を支給しました。正社員、嘱託社員に対しては5万円~12万円(子育て世帯には人数に応じた支援)、社会保険加入のパート・アルバイトには一律1万円の支給です。
報酬に含むかどうか
一般的にインフレ手当は「生活支援」が目的であり、手当を受給した従業員は通常の生計に充てると考えられています。通常の給与等と同じく、労働の対償である報酬に含めるべきだと考えられ、社会保険や雇用保険料、税金の対象になります。
また、月額手当として毎月支給する場合、固定的賃金の変動として社会保険料の随時改定(月額変更届)が必要です。届出を行っていなかった場合には、調査で遡って保険料を徴収される可能性もありますので注意しましょう。
就業規則の改定が必要
賃金に関する規定は就業規則の「絶対的記載事項」のひとつです。この賃金には基本給に加えて各種手当も含まれます。
つまり、就業規則(賃金規定)には支給する手当の名称や金額、支給基準等を明記する必要がありますから、あらたにインフレ手当を設けて、月々給与に含めて定期的に支給する場合には就業規則の改定および労働基準監督長へ届出をしなければなりません。
一時金・月額支給それぞれのメリット・デメリット
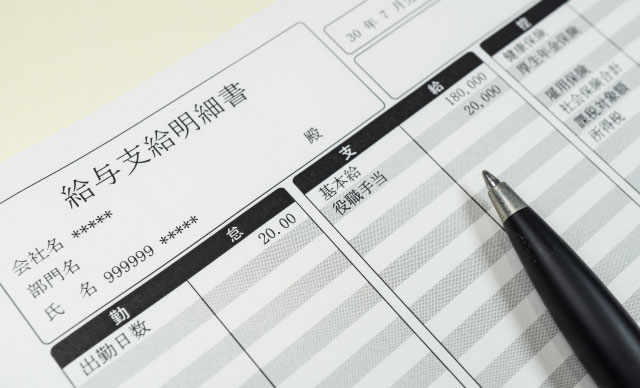
インフレ手当を一時金で支払う企業が多いことは先述したとおりですが、一時金・月額支給のどちらにもメリット・デメリットがあります。それぞれのメリット・デメリットを知り、自社に適する方法を選びましょう。
一時金(賞与)で支給する場合のメリット・デメリット
一時金として賞与に追加して支給する場合には就業規則の変更が要りません。これは企業にとって一番のメリットであると言えます。また、そもそも賞与は支給有無や支給額が業績など企業の裁量で決められますから、次回も必ず支給しなくてはならないということもありません。
一方で、仮に一度だけの支給でも、企業側には賞与分と手当分の資金が一度に流出してしまいます。企業にとって資金面でのインパクトが大きくなるのはデメリットでしょう。また、賞与に上乗せする場合、インフレ手当の金額によっては支給の事実を従業員に把握されにくい場合もあるでしょう。せっかく支給しても、企業側の誠意を感じてもらいにくいことも考えられます。
月額手当として支給する場合のメリット・デメリット
月額手当として支給する場合、支出を平準化できるメリットがあります。受給する従業員側にとっても食費やガソリン代など月々増える支出に対応させやすく、従業員のモチベーション維持や企業に対する信頼につながります。
デメリットは就業規則の変更および届出、社会保険の臨時改定手続きといった煩雑な手続きが必要となることです。
また、手当の額によっては税金や社会保険料の上がり幅が大きくなり、企業がいうほど手取りが増えていないと考える従業員もいるかもしれません。給与日には現状の手取り額にそのまま手当額を上乗せした額を受け取れると考える従業員もいると考え、丁寧に説明する必要がありそうです。
就業規則に記載する場合の記載例
最後に、就業規則に記載する場合の記載例を紹介します。参考にしてください。
第〇条 インフレ手当は、急激な物価高等から従業員と家族の生活を支援する目的で、期間を限定して手当を支給することがある。インフレ手当の金額、支給対象期間、支給方法、支給対象従業員については、総務省発表の消費者物価指数、会社の業績、扶養家族の人数等を勘案して個別に決定するものとする。
まとめ
昨今の急激な物価上昇を受け、従業員への生活支援として一時金や月額手当を支給する企業が増えています。
インフレ手当の支給は実質的な賃金低下抑制につながり、従業員のモチベーションアップ、人材定着のためにも有効です。ただし、支給の仕方によっては就業規則や社会保険、給与計算上の煩雑な手続きや、資金面での大きな負担を伴う場合があります。
インフレ手当を導入する際には、従業員・企業の双方にメリットの高い方法を熟慮するようにしてください。





