2021年10月1日から健康保険被保険者証が直接従業員(被保険者に該当する場合は役員も含む)へ交付することができるようになります。旧来は会社に送付され、会社の人事労務担当者から本人へ渡されていました。必然的にこれまでとは異なった業務フローの整備や予想される相談内容への解答方法の均一化(たまたま対応した担当者の主観に依存せず課として統一的な対応)が求められます。
今回は、変更された取り扱いと、改正前後の問題点にフォーカスをあて、確認していきましょう。
改正前の業務フロー
事業主が新規採用者の情報を取得し、資格取得届を所轄年金事務所等へ届け出ます。疑義が生じなければ被保険者証が発行され、事業主へ送付され、事業主から本人に渡されていました。また、新規採用者に限らず、扶養親族が増加した場合や被保険者証の再発行時も同様の流れです。
改正後の業務フロー
事業主が新規採用者の情報を取得し、資格取得届を届出するところは同じです。改正前と同様に届け出た内容に疑義が生じなければ被保険者証が発行されますが、改正後は、保険者が支障がないと認める場合、保険者が被保険者に直接送付することが可能となります。
改正前の課題
企業の人事労務担当者が被保険者証を手渡しするためだけに出社を余儀なくされていた点は看過できない点です。出社するということは少なくとも感染リスクに晒されること、人事労務担当者がテレワーク中であれば業務の中断が発生し、労働生産性が下がることが予想できます。
改正に関する実務上の問題点
今回の改正は保険者からの被保険者証の送付に限って行われるもので退職や社会保険の喪失(例えば労働時間の短縮により社会保険資格取得の要件を満たさなくなった場合)による保険者への(被保険者証の)送付は事業主を経由し送付することが求められます。
懸念される実務上の問題点として以下の内容が予想されます。
- 被保険者証が発送されたか否かの問い合わせ増加
改正前であれば事業主に被保険者証が送付されていたことから本人が自宅を留守にしていても事業主が受け取ってくれていましたが、そのフィルターを通過しなくなります。そうなると各自で郵便物を管理しなければならなくなるということです。また、郵便物を適正に管理できない場合は届いたとしても「まだ届いていない」などの問い合わせが増えることが予想されます。 - 本人の住所の適正把握
本人に送付するということは住所変更の聴取も適正に行っておく必要性が高まります。これは資格取得時に限ったことではなく、新たに親族を扶養する場合にも被保険者証が発行されるため、転居を行っている場合は然るべきタイミングで住所を把握しておく必要があります。現在はマイナンバーの連携により年金事務所でも住所情報の把握は容易になりましたが、住民票住所と実際が異なっている場合や便宜上住民票上の住所と異なっている場合(例えば親の介護のため自宅を長期間空けている)などは想定できます。 - 健康保険被保険者資格証明書発行の増加
健康保険被保険者資格証明書とは被保険者証が交付されるまでの間に医療機関を受診する必要がある場合に事業主または被保険者からの申請に基づき、被保険者証が交付されるまでの間に限って有効な証明書です(有効期限は証明日から20日間)。確実に増加するとは断言できませんが、自身で郵便物の管理をしなければならなくなることから、慎重を期すということも考えられます。
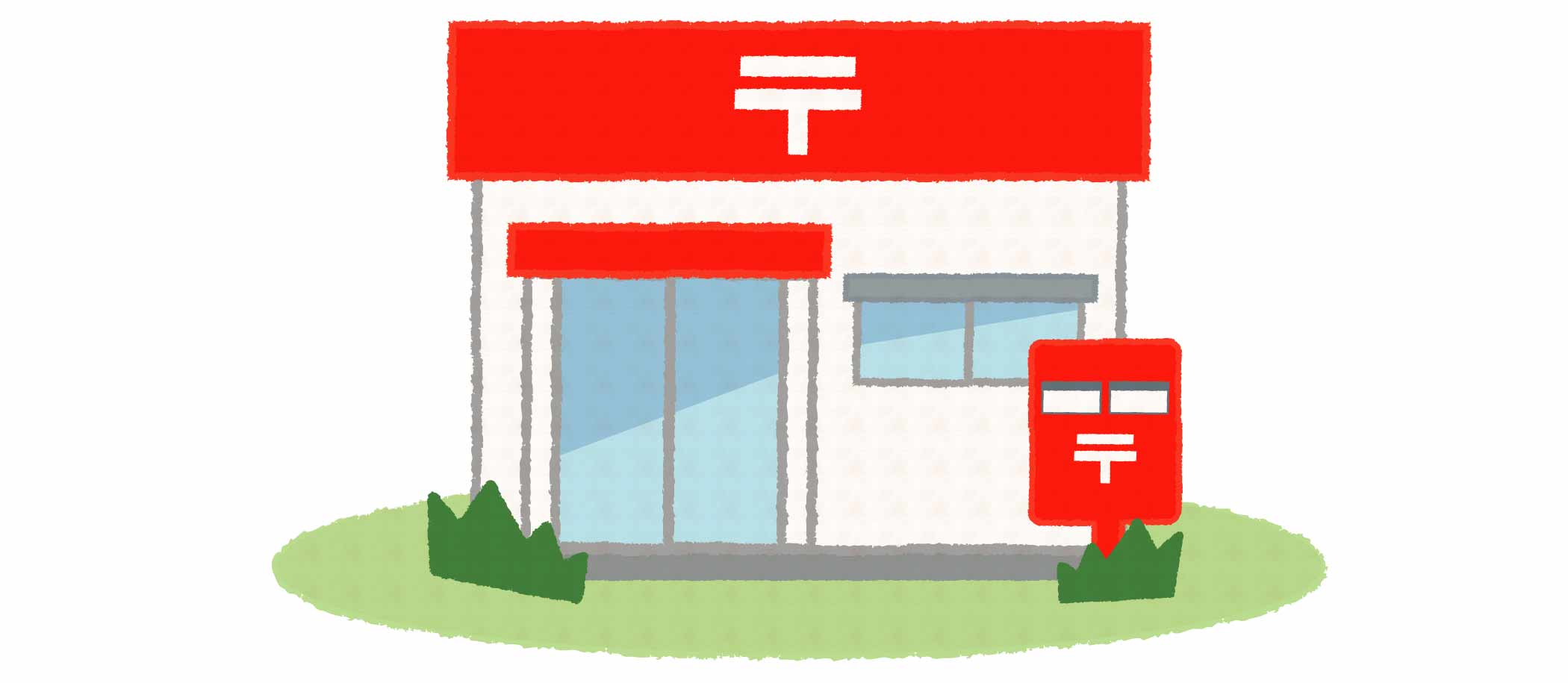
その他留意する点
本人への保険証交付について、資格取得の手続き用紙の変更の可能性があります。これは、現在の書式には交付先の情報を記載する欄がなく、会社宛てなのか本人宛なのかの峻別がつかず、かつ、本人交付の場合は事業所整理記号・本人整理番号を会社に通知しても交付した旨の通知は必須でないとしていることから運用していく中で疑義が生じていくものと考えます。
他の論点として外部社労士に被保険者証発行(資格取得の手続きなど)を委託している場合、本人から社労士宛に確認の連絡(自宅宛てに被保険者証はいつ頃届くかなど)が多くなることが予想されます。
また、マイナンバーカードが保険証の代わりとなる改正についても一時不具合が生じた関係で見直しが図られましたが、基盤を整え、10月以降に再度進めていくこととなっています。
業務フローとしてどの部分の運用を変更する必要があるか
本人への周知
社会保険は要件を満たせば役員であっても一般の従業員であっても資格取得の対象となります。運用フローの周知漏れは信頼関係に亀裂を生じさせるだけでなく、日常生活レベルで不都合が生じる可能性が高い内容であることから、改正前に周知しておくことが必須となります。これは、繰り返しになりますが、被保険者証の発行は採用時に限ったことではなく、扶養親族の増加や被保険者証の紛失もあり得る点も見逃せません。また、会社・本人間での送付先の住所の連携についても資格取得届等の作成は会社の人事労務担当者(または外部社労士)が担うことが一般的であることから、然るべきタイミングで報告を求める通知を出すことが必要です。





